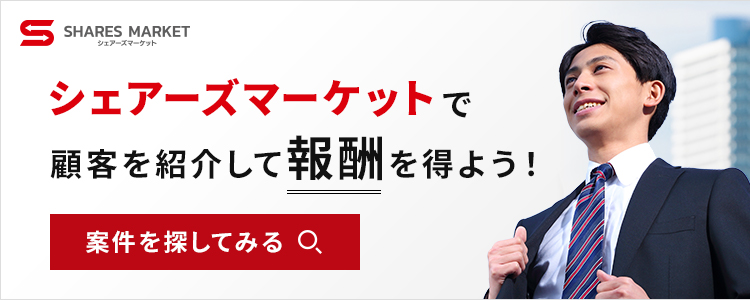副業をしたい方へ
初心者でも今すぐに副収入を稼ぐことができる簡単な方法とは…?
シェアーズマーケットで始める“副業のイロハ”をご紹介します!
副業で収入があった場合住民税はいくらからかかるの?
副業をした場合、その所得金額に応じた税金を支払わなければいけません。
地方税である“住民税”もそのうちの1つであり、あらかじめその仕組みや支払方法などを把握していないと、後々問題となってしまう場合もあります。
自分が損をしないためにも、税金にまつわる知識を身につけておくことが大切です。
ここでは、副業を行っている場合の住民税について、その仕組みや計算方法、支払い方法、注意点などを解説していきます。
住民税とは?所得がいくらから支払う必要があるのか
まずは、住民税とはなにか、その仕組みについて解説します。
住民税は、税金の中でも副業で収入を得た場合には、必ず確認しなければいけない項目の1つです。
収入が少なければ増額されることはない、と思っている方は特に確認しておいてください。
副業の所得には必ず住民税がかかる
「副業の収入が20万円を超えていなければ、申告の必要や支払う税の増額はない」という話をよく聞きますが、これは間違いです。
副業で収入を得た場合には、必ずその所得に応じた住民税が加算されます。
これは「所得税」と「住民税」が混同されてしまっていることが原因です。
所得に対してかかる税金には所得税と住民税がありますが、副業の所得が20万円以下であれば副業分の所得税はかからないため、確定申告をする必要はありません。
しかし、住民税は所得税とは取り扱いが別となっているため、きちんと所得を申告して副業分がプラスされた税額を支払わなければいけないのです。
国に支払う所得税と市区町村に支払う住民税
所得税と住民税は、それぞれの税を管轄している行政機関が異なります。
先程の申告の有無の違いは、申告をする先や税金額の計算方法の違いによって生まれものです。
所得税
所得税は国に対して支払う“国税”であり、その管轄は税務署が行っています。
申告・納税をするためには、“確定申告”を所轄の税務署で行い、1年間の所得税の金額を決めなくてはいけません。
所得税の金額は課税対象となる所得に対して、その金額に応じた税率をかけることで算出することができます。
所得金額 × 税率 = 所得税
日本は所得税において累進課税制度を取っているため、所得の金額が高くなればなるほど、その税率も高く設定されます。
詳しくは、「副業で収入があった場合所得税はどうなるの?」で解説しているので、こちらをご覧ください。
住民税
住民税は市区町村に対して支払う“地方税”の一種であり、その管轄は各市区町村の役所が行っています。
所得税とは異なり、前年の所得から計算した税金額を当年に支払いが発生するため、当年の所得有無に関わらず納付しなければなりません。
住民税の計算方法は、「所得割」「均等割」「利子割」「配当割」「株式等譲渡所得割」の5つの要素からなっており、以下によって求められます。
住民税 = 所得割 + 均等割 + 利子割 + 配当割 + 株式等譲渡所得割
所得割は、給与所得から所得控除を差し引いた金額に対して、10%の税額をかけて算出します。(県民税4%+市民税6%)
この時、配当控除、外国税額控除、寄附金税額控除などの税額控除があった場合には、算出された所得割から差し引かれます。
均等割は、所得金額に関わらず均等に加算される税額です。
その金額は都道府県・市区町村によって異なり、相場は3,000~5,000円になります。
この他に、利子割・配当割・株式等譲渡所得割などの特定所得があった場合には、その金額を加算することで算出されるのが住民税です。
住民税の支払い方法は?どうやって支払う?
では、住民税を支払うためには、どのようにすればいいのでしょうか。
ここからは、実際に住民税を支払うために必要な手続き、支払い方法について解説していきます。
副業の所得を役所に申告する必要がある
まずは、各市区町村の役所に申告をする必要の有無を確認してください。
副業の所得が20万円を超えている場合、確定申告をすることで税務署から役所に対して住民税額の連絡が行われるため、自分で申告をする必要はありません。
副業の所得が20万円を超えていない場合、副業分の所得税はかからないので確定申告をする必要はありませんが、別途住んでいる市区町村の役所に対して所得を申告する必要があります。
確定申告と同様3月頃に申告をし、それに応じた住民税の金額の支払いが必要です
住民税の支払い方法
住民税の支払い方法は、「普通徴収」と「特別徴収」の2つに分かれています。
普通徴収
普通徴収は、送られた納付書による手続きを個人で行う支払い方法です。
年間の住民税が10回分の納付書となって送付されます。
納付方法は、銀行や公共機関、コンビニなどに行って支払うか、預金口座からの引き落としも手続きによって可能です。
特別徴収
特別徴収は、企業に勤務している場合に毎月の給料から天引きされる支払い方法です。
正社員・アルバイト・パートなどの雇用形態に関わらず、源泉徴収を行っている場合は、特別徴収の対象となります。
住民税を“特別徴収”にすると副業がばれる?
副業が勤務先の企業にばれてしまう原因として、副業によって加算された住民税額が挙げられます。
そのため、勤務先が副業禁止であった場合、ばれないための対策として、普通徴収による住民税の支払いが必要です。
しかし、最近では住民税の特別徴収義務化が進んでおり、平成29年度からすべての事業主に対して原則として住民税の特別徴収を徹底するように義務付けられています。
企業によっては、普通徴収による手続きを認めてもらえないこともあるので、注意が必要です。
副業をする際の住民税の納付方法とその注意点
住民税の納付をする時には、いくつか注意しなくてはいけない点があります。
- 申告・支払期限を把握しなければいけない
- 転職・退職時の支払いに注意が必要
- クレジットカードの場合、領収証が発行されない
特に、この3点には十分注意をして、納付手続きを進めていきましょう。
申告・支払期限を把握しなければいけない
住民税の支払期限は、確定申告と同じように3月15日です。
副業で得た1年間の所得が20万円以下の場合でも、各市区町村の役所に対して住民税の申告書を提出する必要があるので気をつけてください。
申告書は役所のHPからダウンロード可能です。 申告期限に余裕を持って提出することができるように、あらかじめ用意をしておきましょう。
住民税の税額は毎年1月1日~12月31日までの所得から計算されますが、納税時期は翌年の6月から翌々年の5月までの期間で行われます。 その年の間にA市からB市に引っ越したとしても、納税先はA市から変わらないので注意してください。
転職・退職時の支払いに注意が必要
企業に勤務している場合、住民税は毎月の給与から天引きされます。
そのため、年度の途中で転職・退職をした場合、納付されていない分の住民税を個人で支払い手続きをしなければいけないかもしれません。
転職した場合の住民税の支払い
給与所得者の場合、住民税の支払いは原則として給与からの天引きによって行われます。
そのため、転職をしたとしても基本的には転職先にて特別徴収を引き継ぎ、転職先の給与から支払いが可能です。
ただし、支払い引き継ぎの手続きに2ヶ月程度の期間を要する場合もあります。
もし、手続きが間に合わない場合には、前職の会社に依頼してまとめて数ヶ月分の住民税を天引きしてもらう、または普通徴収に切り替えて自分で納税する、などの対応をしてください。
退職した場合の住民税の支払い
企業から退職をして次の就職先が決まっていない場合は、その退職した日にちによって、支払いの対応が変わります。
6月1日~12月31日退職した場合…
退職した月以降の住民税を普通徴収に切り替えて納税する必要があります。
あらかじめ退職前に支払い方法の変更を会社に依頼するか、役所にて手続きをしてください。
希望をすれば退職した月から翌年6月までの住民税を、退職した月の給与または退職金から一括支払いをしてもらうことも可能です。
1月1日~5月31日に退職した場合…
原則として退職した月の給与から残った住民税を一括徴収されます。
退職した月の給与が住民税の徴収額より少ない場合は、普通徴収に切り替えて自分で支払うことも可能です。
クレジットカードの場合、領収証が発行されない
住民税はクレジットカードで納付することができます(納税システムが整備されていない自治体を除く)。
クレジットカードで納付をすることで、24時間いつでも納付できる、クレジットカードのポイントがつくなど、様々なメリットがありますが、デメリットとして領収証が発行されません。
支払い内容を確認するためには利用明細を確認するか、個別で納税証明書を発行する必要があります。
ただし、納税証明書の発行には、手続きから日数がかかる場合もあるので注意です。
まとめ
副業によって収入を得た場合には、その所得に応じた住民税を支払う義務があります。
所得が20万円以下であった場合には、確定申告の必要がない代わりに、各市区町村の役所に対しての所得申告が必要です。
企業に勤めている場合には、原則として特別徴収が適用されますが、転職・退職をした場合の住民税の取り扱いには十分注意をしてください。
自分が稼いだお金を正しく守るためにも、副業を始めようと思っている際は、あらかじめ住民税とはなんなのか、その計算の方法、支払い方法を知っておくようにしましょう。